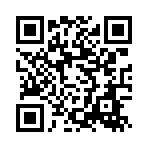2011年04月14日
歴史に想いを馳せてみました。
お天気がいい毎日が続いているので、相変わらず花粉が絶好調に飛んでいます。
緑が多い分、花粉も都会に比べて多いので、こちらにお越しのお客様は花粉対策を充分にされて、どうぞお出かけください。
さてさて、随分毎日暖かくなってきて、冬眠中のクマ達もそろそろ活動しだす頃ですね。
今日は、冬眠からクマが目覚める前に、クマが割と出没しやすいけれど行ってみたい、隠れざる観光スポットをてくてく歩いてみましたので、2ヶ所だけですが、ご紹介いたします。
まずは、古事記の「天の岩戸伝説」にまつわる、「天の岩戸岩」に行ってみました。

緑が多い分、花粉も都会に比べて多いので、こちらにお越しのお客様は花粉対策を充分にされて、どうぞお出かけください。
さてさて、随分毎日暖かくなってきて、冬眠中のクマ達もそろそろ活動しだす頃ですね。
今日は、冬眠からクマが目覚める前に、クマが割と出没しやすいけれど行ってみたい、隠れざる観光スポットをてくてく歩いてみましたので、2ヶ所だけですが、ご紹介いたします。
まずは、古事記の「天の岩戸伝説」にまつわる、「天の岩戸岩」に行ってみました。
馬羅尾高原キャンプ場の東下、神話の小径の看板を目印に進んでいきます。
JR信濃松川駅より、車で約15分ほどです。

ひたすら歩いていきます。

高原の中腹に車を停めて、徒歩でしばらく小径を歩いていると、目の前にとっても大きな岩が立ちはだかっていました!!
幅約6m、高さ約6m、奥行約9mの大きな岩です。
天狗の顔っぽい岩のかたち、分かりますでしょうか?

はるか昔、天照大御神という太陽の神様が、身を隠していたことに名前が由来しているという説や、
この岩の北側の山に位置する六部岩といわれるところに、大昔、六部夫妻という夫婦がおり、有明山に住んでいた心よからぬ天狗と、六部が争いを起こし、怒った六部がかっとなって天狗を蹴りあげたところ、山から落ちた場所が、この岩のうえだったという説もあります。
お次はこちら、桜沢遺跡よりさらに山奥にございます、「祖父が塚(じいがつか)古墳」です。

こちらも、JR信濃松川駅より、車で約15分ほどのところにあります。

石室の内部も、恐る恐る撮影してきました。
横穴式石室で、直径16m、高さ2.5mです。

松川村の文化財史によると、
古墳時代後期6世紀末に構築された円墳だそうで、明治10年代に開口されたが、既に盗掘されており、出土品は失われていましたが、一部の玉類、銀環などの装具一式は、宮内庁の書陵部に所蔵されているそうです。
この古墳は、当時、鼠穴集落付近にあった村の首長一家の墓と考えられている大変貴重な文化財です。
<祖父が塚古墳>
★種 別:史跡
★所有者:松川村
★所在地:北安曇郡松川村鼠穴4295番地2
★村文化財指定日:昭和58年1月5日
少しずつ村の文化財をご紹介していきますので、どうぞ気長にお待ちください☆
JR信濃松川駅より、車で約15分ほどです。
ひたすら歩いていきます。
高原の中腹に車を停めて、徒歩でしばらく小径を歩いていると、目の前にとっても大きな岩が立ちはだかっていました!!
幅約6m、高さ約6m、奥行約9mの大きな岩です。
天狗の顔っぽい岩のかたち、分かりますでしょうか?
はるか昔、天照大御神という太陽の神様が、身を隠していたことに名前が由来しているという説や、
この岩の北側の山に位置する六部岩といわれるところに、大昔、六部夫妻という夫婦がおり、有明山に住んでいた心よからぬ天狗と、六部が争いを起こし、怒った六部がかっとなって天狗を蹴りあげたところ、山から落ちた場所が、この岩のうえだったという説もあります。
お次はこちら、桜沢遺跡よりさらに山奥にございます、「祖父が塚(じいがつか)古墳」です。
こちらも、JR信濃松川駅より、車で約15分ほどのところにあります。
石室の内部も、恐る恐る撮影してきました。
横穴式石室で、直径16m、高さ2.5mです。
松川村の文化財史によると、
古墳時代後期6世紀末に構築された円墳だそうで、明治10年代に開口されたが、既に盗掘されており、出土品は失われていましたが、一部の玉類、銀環などの装具一式は、宮内庁の書陵部に所蔵されているそうです。
この古墳は、当時、鼠穴集落付近にあった村の首長一家の墓と考えられている大変貴重な文化財です。
<祖父が塚古墳>
★種 別:史跡
★所有者:松川村
★所在地:北安曇郡松川村鼠穴4295番地2
★村文化財指定日:昭和58年1月5日
少しずつ村の文化財をご紹介していきますので、どうぞ気長にお待ちください☆
Posted by松川村観光協会at10:17
遺跡